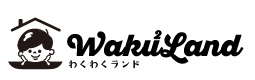著者:家具通販わくわくランド編集部
家具・インテリアの専門店「わくわくランド」が運営するオウンドメディア編集部。
家具販売の現場で培った知識やお客様からのリアルな声をもとに、暮らしを快適にする家具選びのコツやインテリアのアイデアを発信しています。
スタッフが実際に扱う家具やお客様の声をもとに、暮らしに寄り添ったリアルな情報をお届けします。
赤ちゃんの誕生を迎える準備で、特に悩みやすいのが「ベビーベッド選び」。種類やサイズ、素材もさまざまで、「本当に必要?」「いつまで使えるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか?この記事では、ベビーベッドを選ぶ際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説し、後悔しない選び方をサポートします。
はじめに|ベビーベッドは必要?
家庭によって「必要・不要」は分かれる
赤ちゃんの寝床として定番の「ベビーベッド」ですが、すべての家庭に必要というわけではありません。寝室の広さ、生活スタイル、赤ちゃんとの寝方(添い寝or別々)などによって、必要性は大きく変わります。たとえば、寝室が狭く布団で添い寝する家庭ではスペース的にベビーベッドが不要な場合もあります。
一方で、赤ちゃんだけの安全な空間を確保したい場合や、兄弟姉妹やペットとの生活がある家庭では、事故を防ぐ意味でもベビーベッドの設置が効果的です。まずは自宅の環境や子育ての方針に合わせて、必要かどうかを見極めましょう。

ベビーベッドのメリットとデメリット
ベビーベッドの最大のメリットは、赤ちゃん専用の安全なスペースが確保できることです。床より高い位置にあるため、ホコリや冷気を避けられ、兄弟やペットからの接触リスクも低くなります。加えて、ママ・パパが夜中のおむつ替えや授乳のときに立ったまま世話がしやすいという利点もあります。
一方で、サイズが大きく場所を取る点や、使用期間が短い(約1〜2年)といったデメリットも。価格も安くはないため、購入に迷う方も多いでしょう。最近は折りたたみタイプやリメイク可能な多機能タイプも増えており、こうした点を考慮して自分たちの暮らしに合ったものを選ぶことが大切です。
ベビーベッドを選ぶときの5つのポイント
① サイズと設置スペースの確認
ベビーベッドは意外と大きいため、まず確認すべきは「置く場所に合ったサイズかどうか」です。スタンダードサイズ(約120×70cm)は長く使えますが、スペースに余裕が必要です。一方で、ミニサイズ(約90×60cm)は設置しやすく、特にワンルームや寝室が狭い家庭に人気。ただし使用期間は短めになるため、ライフスタイルに応じた選択が重要です。ベッドの周囲には大人が通れる動線も必要なので、設置後の全体的なレイアウトも想定して選びましょう。

② 高さ調整とママ・パパの腰への負担
ベビーベッドの高さは、育児の快適さに大きく影響します。床板の高さを調整できるモデルであれば、赤ちゃんを抱き上げたり寝かせたりするときに腰への負担を軽減できます。特に産後のママにとっては、毎日の動作が負担になりやすいため、高さ調整は必須機能といえます。また、赤ちゃんの成長にあわせて低くできるタイプなら、安全性も長く保てるため、成長過程にフィットする設計を選ぶのがポイントです。
③ 素材の安全性と赤ちゃんへのやさしさ
赤ちゃんの肌に直接触れるベビーベッドは、使用されている素材の安全性も見逃せません。おすすめは天然木を使用した無垢材や、ホルムアルデヒドなど有害物質の少ない塗装仕上げのものです。SGマークやF☆☆☆☆(エフフォースター)などの表示がある製品は、安全性が高い証拠です。化学物質のにおいが少ないものを選ぶことで、赤ちゃんのアレルギーや健康リスクを避けることができます。
④ キャスター・収納などの便利機能
育児を少しでも楽にするために、ベビーベッドの機能性も重視したいポイントです。キャスター付きのモデルなら、掃除や部屋の移動もスムーズで、寝かしつけの際も便利です。また、ベッド下に収納スペースがあると、おむつやタオルなどをすぐに手が届く場所に保管できてとても実用的。限られたスペースを有効に使えるよう、移動性や収納力も比較して選ぶのがおすすめです。

⑤ 組み立てやすさと使い勝手
ベビーベッドは、出産前後の限られた時間の中で設置することが多いため、「組み立てやすさ」や「使い勝手の良さ」も見逃せません。工具なしで組み立てできるタイプや、パーツが少ない構造のものは、初心者でも安心して扱えます。また、マットレスの設置、柵の開閉のしやすさなども日々の使いやすさに直結します。口コミやレビューで実際の使用感を確認するのも良い方法です。
タイプ別|ベビーベッドの種類と選び方
スタンダードタイプ
最も一般的な「スタンダードタイプ」は、約120×70cmのサイズで、赤ちゃんが1歳〜2歳までゆったり使えるのが特徴です。広めのスペースを確保できるため、動きが活発になってからも安心して寝かせられます。耐久性が高く、兄弟が生まれた際にも再利用しやすい点も魅力。収納付きや高さ調整機能など、種類も豊富です。ただし、部屋の広さが限られている家庭では圧迫感を感じることもあるため、設置前にスペース確認が必要です。
添い寝タイプ(サイドオープン)
添い寝タイプは、片側の柵が開閉できるサイドオープン仕様のベビーベッドです。親のベッドと高さを合わせて横付けできるため、夜間の授乳やおむつ替えが楽にでき、寝かしつけにも便利。赤ちゃんのそばで眠れる安心感がありながら、しっかりと境界があるため安全性も高いです。高さ調整の幅が広いモデルを選べば、さまざまなベッドと組み合わせられます。ただし、床に段差があると固定しにくいため注意が必要です。

折りたたみタイプ
折りたたみタイプのベビーベッドは、省スペースで収納しやすく、使わないときにコンパクトに片付けられるのが最大の魅力です。来客時や日中だけ使用したい方、また里帰りや旅行先に持っていきたい方にもぴったり。組み立ても簡単なものが多く、女性一人でも扱いやすい仕様です。ただし、フレームがやや軽量なため、安定感ではスタンダードタイプにやや劣る傾向があります。利用目的を明確にして選ぶのがおすすめです。

ミニサイズタイプ
ミニサイズタイプは、限られたスペースでも設置しやすいコンパクトなベビーベッド。標準サイズよりも一回り小さい約90×60cm前後が主流で、ワンルームや寝室が狭い家庭に人気です。見た目にも圧迫感がなく、お部屋の雰囲気に馴染みやすいのもポイント。ただし、赤ちゃんの成長によっては使用期間が短くなることもあるため、早めにベビーベッドを卒業する可能性を考えて選びましょう。収納付きや折りたたみ式のものもあります。
安心して使うために確認したい安全基準
SGマーク・PSCマークとは?
ベビーベッドを選ぶうえで、まずチェックしたいのが「SGマーク」と「PSCマーク」の有無です。SGマークは製品安全協会が定めた基準をクリアした製品に与えられ、安全性が保証されています。PSCマークは、消費生活用製品安全法に基づき、国が定めた基準を満たしていることを示すマークです。どちらも法的に厳しい安全性が求められており、赤ちゃんのベッドにおいては必須レベルの確認ポイントといえるでしょう。通販などで購入する際は、商品ページのマーク表示を必ず確認しましょう。
チェックすべき構造・塗装・隙間
マークの有無だけでなく、実際の構造や素材にも注目しましょう。たとえば、すのこの隙間が広すぎると赤ちゃんの手足が挟まる恐れがあります。JIS規格では、すのこの隙間は30mm以下が推奨されています。また、使用されている塗料がホルムアルデヒドなどの有害物質を含んでいないかも重要なポイント。表面が滑らかでトゲや欠けがなく、口に触れても安全な仕上げになっているかを確認しましょう。安全性は赤ちゃんの命を守る最優先事項。細部まで丁寧に確認することが大切です。

使用期間の目安と卒業後の活用アイデア
ベビーベッドはいつまで使う?
一般的にベビーベッドの使用期間は、生後0ヶ月から1歳半〜2歳頃までが目安です。ただし、赤ちゃんの成長スピードや寝返り・つかまり立ちのタイミングによって、卒業時期は前後します。つかまり立ちを始めると、転落防止のために床板を一番下まで下げる必要があり、それでも乗り越える危険がある場合は早めの卒業を検討しましょう。メーカーごとに対象月齢や体重制限が異なるため、購入前に確認しておくと安心です。
収納棚やベンチなどへのリメイク活用
ベビーベッドを使い終わったあと、「もう使えないから捨てるのはもったいない…」と思う方も多いはず。最近では、ベビーベッドをそのまま「収納棚」や「子ども用ベンチ」にリメイクできる商品も増えています。パーツを取り外して本棚にしたり、おもちゃ収納として使えるモデルもあり、長く活用できるのが魅力です。リサイクルやサステナブルの観点からも、リメイク対応のベビーベッドは人気が高まっています。使い終わったあとの使い道も想定して選ぶのが賢い選び方です。
おすすめのベビーベッド3選
コンパクトで使いやすいミニタイプ
成長に合わせて長く使える多機能タイプ
おしゃれで安全な天然木ベッド
まとめ|赤ちゃんと家族に合ったベビーベッドを選ぼう
選び方のポイントを振り返り
ベビーベッドを選ぶときは、まず「設置スペースに合うか」をチェックしましょう。そのうえで、高さ調整機能や素材の安全性、便利な機能面もしっかり比較することが重要です。さらに、スタンダードや添い寝タイプ、折りたたみなど、使い方に合ったベッドの種類を選ぶことも重要。赤ちゃんの成長スピードや生活スタイルに合わせて選べば、短期間でも満足度の高い使い方ができます。選び方をしっかり押さえて、自分たちにぴったりのベッドを見つけましょう。
ベビーベッド選びで大切にしたいこと
ベビーベッド選びで一番大切なのは、「赤ちゃんの安全」と「家族の暮らしやすさ」を両立できるかどうかです。見た目や価格も大事ですが、使い勝手や安心感が育児中のストレス軽減にもつながります。また、使用後のリメイクや再利用のことまで考えると、より満足度の高い選択が可能です。機能やデザインだけにとらわれず、赤ちゃんと家族が笑顔で過ごせる毎日をサポートしてくれる一台を選びましょう。